 |

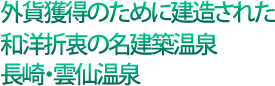
雲仙は江戸時代に開発が始まり、のちに外国人の避暑地として発展を遂げていく。昭和10年に建設された雲仙観光ホテルは日本のリゾートホテルの草分け的存在だ。和洋折衷の名建築と源泉かけ流しの酸性硫黄泉が共存する、宿泊できる貴重な文化遺産になっている。
雲仙温泉 雲仙観光ホテル
●住所:長崎県雲仙市小浜町雲仙320
●泉質(お糸地獄):酸性・含鉄・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩泉
●泉温:93.5度
●pH:2.0
●湧出量:不明
●日帰り入浴:11:00~17:00(1000円/食事必須・入浴のみ不可)
TEL:0957-73-3263
●住所:長崎県雲仙市小浜町雲仙320
●泉質(お糸地獄):酸性・含鉄・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩泉
●泉温:93.5度
●pH:2.0
●湧出量:不明
●日帰り入浴:11:00~17:00(1000円/食事必須・入浴のみ不可)
TEL:0957-73-3263

雲仙観光ホテルの浴室。天井のドームが印象的。壁のタイルはアールデコ調でシンプル

中央階段のたたずまいは創業以来変わっていない。柱は名栗仕上げ。手すりはインドネシア産のジェルトンを使用

広さ42㎡のラグジュアリーツイン「プレミアム」。時代の変化に合わせ、2部屋をつないで居住性を高めた

バーの床のタイルは創業当時のまま。手焼きのタイルを並べ、細やかな職人の手作業がよくわかる

和と洋の建築様式が融合している。雲仙の街並みには統一感がある

夜のコースメニューのオードブル「人参のムース」。素材の味を生かした現代風フレンチで、野菜の味が強い

お糸地獄の源泉付近。熱水からむせ返るような噴煙がたなびく
日本最古のリゾートホテルといえば、栃木県日光市にある「日光金谷ホテル」ということで名が知られている。
日光東照宮の楽師をしていた金谷善一郎が、外国人の宿泊用にと自宅を改装し、明治6年(1873)に「金谷カッテージ・イン」を開業した。
明治11年(1878)6月には、英国人旅行家のイザベラ・バード女史も訪れ、この金谷の邸宅をベースに、何日もかけて東照宮や周辺の観光地へ足を運んでいる。
そして、明治26年(1893)には、2階建て洋室30室の「金谷ホテル」が誕生する。
明治維新の開国によって外国人が日本にやってくるようになると、全国の観光地にも変化が訪れる。
日光のような避暑地に、洋式のホテルが建造されるようになるのだ。
いま現存する黎明期の主なリゾートホテルには、次のようなものが挙げられる。
開業年とともに記載してみよう。
明治 6年(1873)日光金谷ホテル(栃木)
明治11年(1878)富士屋ホテル(神奈川)
明治27年(1894)万平ホテル(長野)
昭和 4年(1929)六甲山ホテル(兵庫)
昭和 8年(1933)上高地帝国ホテル(長野)
昭和 9年(1934)蒲郡クラシックホテル(愛知)
昭和10年(1935)雲仙観光ホテル(長崎)
昭和11年(1936)川奈ホテル(静岡)
昭和12年(1937)赤倉観光ホテル(新潟)
これらはいずれも、訪日外国人を受け入れるために造られた、日本のクラシックホテルだ。
今回の温泉めぐりで足を運んだのは、長崎にある「雲仙観光ホテル」。
温泉のあるクラシックホテルとして、ぜひ一度は行ってみたかった場所だ。
雲仙は、古くは信仰対象の山として、温泉山(うんぜんざん)と呼ばれていた。
大宝元年(701)に、行基によって温泉山満明寺が建立され、これが始まりと考えられている。
8世紀初頭に記された『肥前国風土記』には、すでに温泉山を開発していた高木津座という「山の神」の存在について触れられている。また、噴煙や高温の水蒸気が立ち上る現在の雲仙地獄についても、「峰湯泉(みねのゆのいずみ)」として紹介されている。
16世紀になると、島原は、大名有馬晴信の入信によってキリシタン文化が開花する。
だが、江戸初期にキリシタン弾圧が強まると、雲仙地獄での熱湯の拷問により、33名が殉死するという暗い歴史を引きずることになる。
温泉の開発が始まったのは、島原の乱(1637-1638)の後のこと。
藩主となった松平忠房は、城下や寺社の復興に着手し、島原藩の認可を受けた加藤善左衛門が、承応2年(1653)に初の共同浴場「延暦湯」を開く。その子、小左衛門は、旅館業・湯元の祖に当たるとされている。
明治期になり、避暑のために外国人が訪れるようになると、当初は「古湯」の湯宿が彼らを受け入れていた。だが登山客の増加に対応するために「新湯」地区が開発され、日本人との混浴を避けて新湯が外国人専用となった。
大正2年(1913)には、県営雲仙ゴルフ場、テニスコートが開場。外国人避暑客に向けた雲仙娯楽館も開設される。
雲仙観光ホテルの資料によると、明治末期に日本を訪れた外国人は約1万5000人。大正期には3万人を超え、昭和初期には4万人前後にまで達したとある。
大正から昭和初期にかけて、訪日外国人が消費する外貨は輸出額の3~4%を占め、経常収支の大幅な赤字を改善する収入源となった。そのため、観光立国政策が推進され、外貨獲得に向けて誘致策が講じられていくことになる。
国の施策として、昭和9年(1934)3月、雲仙は瀬戸内海、霧島とともに、日本初の国立公園に指定される。
雲仙観光ホテルの竣工は、翌年の昭和10年(1935)10月10日。
すでに、大正12年(1923)には上海-長崎の上海航路が就航されていて、雲仙の人気が高まっていた頃だ。
赤い瓦葺きの切妻屋根の日本建築に、スイスシャレーに見られる丸太の骨組み、溶岩石の外壁が印象的なハーフティンバー様式が融合。東洋と西洋の美が一体となった、独特な建築様式を採用している。
のちに建設される雲仙のホテルは、ここをまねて赤屋根に統一され、雲仙の街並みが調和の取れたものとなる、景観保全のさきがけとなった。
2003年に国の登録有形文化財に指定されたことを契機に、2004年から6期にわたるリニューアル工事が実施される。
現在、80周年を超えているものの、手斧(ちょうな)で柱に刻まれた名栗仕上げや、中央階段の手すり、エントランスの真鍮のドアノブなど、至る所が創業当時のまま残されている。
ホテルの担当者曰く、「修繕時に文化財を守るような気持ちで手を加えてきたため、職人も当時の形を忠実に再現するよう気を配り、だからこそ柱の装飾も残っている」とのこと。
創業者の橋本喜造は、神戸に海運業の橋本汽船を設立し、大阪に堂島ビルヂングを建設した実業家だ。
長崎という港町の影響もあるのだろうか。重厚感の漂うエントランスロビーでくつろいでいると、客船でおもてなしされているような気分になってくる。
夕方の17時30分になると、メインダイニングの前にある銅鑼(ドラ)が鳴った。
オープンを知らせる音色。長崎の中華街のようにエキゾチックで、客船の出航をも思い起こさせる。
近年のリニューアルに際し、ホテル内には、客船のように建物の中で楽しめるバーや映写室、撞球室(ビリヤード室)や1500冊以上を収蔵する図書室などのパブリックスペースが設けられた。
客船のキャビンには、客同士が穏やかな時間を過ごすパブリックスペースの存在が欠かせない。それはホテルも同じだ。
「寒いので、何か羽織られたらいかがですか」
エントランスにいたコンシェルジュが、外に出ようとするご婦人に対して、さりげなく声をかけていた。
声を掛け合うと、旅先での意識が、受け身から能動的に変わるきっかけになる。
パブリックスペースは、客同士やスタッフとの会話が生まれる、大切なコミュニケーションスペースだ。会話が生まれることで、ホテルのホスピタリティ感やグレードが上がっていくのだと思う。
さらに、このホテルには、客船や海外のホテルにはない、さらなるホスピタリティがある。
それが、温泉という雲仙が育む力だ。
雲仙地獄を散策すると、最上部の「大叫喚地獄」では、ごーっという激しい音とともに、温泉の熱水が噴き出している。強い硫黄臭が漂い、蒸気の激しさで視界がさえぎられるほどで、歩いているだけでも薬効がありそうな気がしてくる。
「お糸地獄」という噴出孔が、雲仙観光ホテルの温泉の泉源だ。
約94度の熱水をパイプに通して500m先の館内に引き込み、加水して温度を調節することでようやく入浴できるようになる。
改修により、浴室は新しく生まれ変わった。
水滴が落ちないように工夫されたドーム型の天井は、男女の浴室を合わせると円形となって、創業時のシンメトリーな構造に原点回帰している。
以前はテラスとして使用されていた場所に、新しく露天風呂も設置された。
日本有数の強酸性泉のため、加水しているとはいえ、酸性度は高い。
もちろん、源泉かけ流しだ。
ホテルの快適さと温泉旅館の心地よさを併せ持つこと。
クラシカルな洋館に似合った温泉のあり方とはどのようなものか。雲仙観光ホテルはひとつの方向を、明確に示している。

福岡、佐賀、長崎方面からは、長崎自動車道・諫早ICから国道57号線、小浜温泉経由で約44㎞、60分。最短経路の千々石から県道128号線に入ると道幅が狭いため避けたほうがいい。熊本、宮崎方面から島原半島へは、熊本港からカーフェリーで島原港へ。国道57号線を南西に進んで約20㎞、30分。
< PROFILE >
長津佳祐
ゴルフや温泉、クルーズ、スローライフを中心に編集・撮影・執筆を手がける。山と溪谷社より共著で『温泉遺産の旅 奇跡の湯 ぶくぶく自噴泉めぐり』を上梓。北海道から九州まで自噴泉の湯船を撮り下ろしで取材した、斬新な切り口の温泉本になっている。
長津佳祐
ゴルフや温泉、クルーズ、スローライフを中心に編集・撮影・執筆を手がける。山と溪谷社より共著で『温泉遺産の旅 奇跡の湯 ぶくぶく自噴泉めぐり』を上梓。北海道から九州まで自噴泉の湯船を撮り下ろしで取材した、斬新な切り口の温泉本になっている。

